
作成 2009年12月24日
最終更新 2015年1月16日
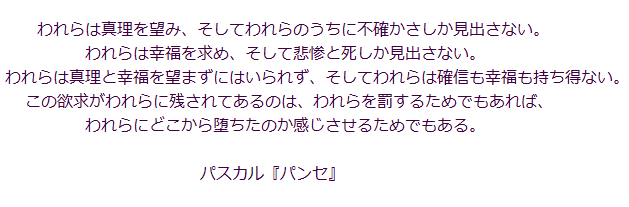
この用語集は、哲学や神学の術語に基づきつつ<世俗化>という現象の現実性と可能性を探究する、
「世俗化論」のために作成してゆくものです。
|
アウラ 独 die Aura 希 aura(息)より ベンヤミンが『複製技術時代の芸術作品』で用いた美学概念。芸術作品の一回的な、「いま・ここ」にあるオリジナルとしての性格を指す。ベンヤミンは芸術の起源を偶像崇拝に見られるような対象への儀式的・礼拝的関係においており、のちの宗教芸術・世俗芸術でも、その真正な作品としての受容は世俗化された形であれ儀式性によって裏付けられているとされる。 写真の登場と共に始まる高度な複製技術の登場は、オリジナルとコピーの関係を転倒させ、ベンヤミンはこれを芸術作品における「アウラの凋落」と呼んだ。しかし実際には新たな複製技術はファシズムによる政治的宣伝のため儀式的効果をもって利用されることになり、この世俗化の逆流現象は美学と政治との関係を一層重要なものとすることとなる。 |
|
アレゴリー 独 die Allegorie 希 alle(別なふうに) + agoreuein(語る) より
寓意とも称する。象徴と同様に抽象的概念を具体物によって知覚可能なものとするものだが、両者の関係は象徴のように調和を持ったものではなく、社会的承認を得てもいない。ゲーテによる区別では、個物のなかに普遍を見るのが象徴であるとすれば、普遍のために個物を求めるのが寓意である。 ベンヤミンは『ドイツ悲哀劇の根源』で、寓意に神学的・歴史哲学的再評価を与えている。寓意が露わにする抽象と具体との隔たりは言語精神の堕罪の表れであり、事物の世界における廃墟のように、衰滅の過程としての歴史を、そしてさらには最期の日における「神的変容」としての反転を予感させるものである。 |
|
永遠回帰 えいえんかいき 独 die ewige Wiederkunft (des Gleichen) あらゆるものが永遠に反復するという教説。バビロン神話、ピラゴラス派、ヘラクレイトス、ストア派、グノーシス主義らにすでに見られるが、ニーチェの『ツァラトゥストラかく語りき』にてユダヤ・キリスト教の終末論に基づく歴史観に対置され、あらゆる瞬間の反復とその永遠なる肯定として知られることになった。 参照: 「ありのままの今」を生きる!「超人」ニーチェの言葉 , All About 「ドイツ語」 |
|
懐疑 かいぎ 独 die Skepsis 希 skepeo(調べる)より ものごとのありのままの姿を知ることが出来るという態度に距離をとり、むしろそれらがどのように現れるかのみを確認しようとする構え。その起源は哲学の始まりとされる前ソクラテス派、枢軸時代より見られるが、「懐疑主義」という学派を初めてうちだしたのは紀元前4~3世紀、エリスのフィロンの一派である。懐疑主義は人間による認識の不確かさ、相対性を強調するが、その目指すところは判断停止により魂の平静状態(アタラクシア)に至ることであった。 中世以降もアウグスティヌス、デカルト、ヒュームらによって懐疑は認識のあり方を検証する方法として発展を見る。その吟味の対象は宗教や倫理にも及ぶが、それらの意義を否定しようとするのではなく、素朴な教義化を防ぎより高次な状態に至らんとする否定神学的な志向をしばしば示す。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 第18~21号:Ich bin, ich existiere (1) ~(4) |
|
神の似姿 かみのにすがた 独 das Ebenbild Gottes 羅 imago dei
創世記第1章27節によれば、「神は御自分にかたどって人を創造された」。故に人間はあらゆる被造物の中で唯一、神の似姿であるとされる。逆に言えば人間が己を知ることが神を知るために不可欠の道ということになり、この点で人間学としての哲学は神学との一致を見る。特に近代社会において、創造者という神の特性は人間の創造力の価値を暗黙であれ神学的に根拠づけるものとなった。 自然一般に対する人間の本質的差異を強調するこの観念は、ユダヤ・キリスト教とそこから世俗化された近代西洋思想を、他の諸宗教・文化からも際立たせることになる。西洋の進歩思想を世俗化の帰結とするレーヴィットは、世俗化論へのブルーメンベルクの批判に対し、世界を変革し支配しようとする近代思想の原動力は、この神の似姿としての人間像でしかありえないと反論している。 |
|
規範 きはん 独 die Norm 羅 norma(直角定規)より 「~であるべし」という、行動の基準や価値判断の根拠をいう。そこでは真か偽か、ということではなく、目的にかなった適切なものであるかどうかが問題となる。例えば倫理学においては規範的に善い行為、美学においては規範に照らして美しいものに価値が置かれる。 規範的(normativ)であるとは、叙述的(deskriptiv)や事実的(faktisch)に対置される形容である。 文化が規範に基づいて形成されるゆえ、文化学とは規範の学である。つまり、自然科学のような経験諸学と異なり、客観的で中立な観点を標榜するものではない。 世俗化論では特に、キリスト教の影響下で規範化された制度、つまり生命・婚姻などの倫理や、政治・経済・歴史などの「主義」が、普遍・妥当性を主張しうるか否か吟味される。 |
|
キリスト教 きりすときょう 独 das Christentum 旧・新約聖書を基本的経典とし、ナザレのイエスを神の子、キリストと信ずる宗教。その伝統により一般に正教会、カトリック、プロテスタントに大別される。 十字架をその中心象徴とする。 周知のように東西ヨーロッパを中心に歴史的発展を見た、世界最大規模の宗教である。教父時代、人文主義やルネッサンスを経て、16世紀宗教改革に事実上始まる世俗化により、一方では政治・文化との調和的統一を喪失して行きつつも、他方で宗教批判を内在させた宗教としてそれらに比類なき影響を与え続けて行くことになった。 |
|
寓意 ぐうい → アレゴリー |
|
偶有性 ぐうゆうせい 独 das Akzidens 希 symbebekos 羅 accidentia ものやことにおける、偶然的なもの。 アリストテレスの定義によれば、ある対象の特性のうち、必然的にも一般的にも帰属しないもの。 例えばある猫が「白毛である」ことは偶有的なことである。なぜなら白毛であることは猫一般にとって必然性を持たず、黒や茶毛でもありうる。また、猫が一般的に白毛であるというわけでもない。 状況や条件で変わりうる付帯性ということで、偶有性は「実体」や「本質」の対義語と見なされる。 ただしキリスト教の伝統では、最後の晩餐でパンと葡萄酒がその姿を変えることなくキリストの肉と血になったという出来事によって、偶有的なものが変わらず実体が変化する、という事態が認められている。このことは聖餐式において何を真の実体と見なすか、という解釈の相違を生み、各教派に分裂をもたらすきっかけともなった。 |
|
啓示 けいじ 独 die Offenbarung 英 revelation 希 apokalypsis 羅 revelatio(覆いを取る) 隠された真理が顕わになること。特に旧約聖書では預言者に与えられる神の救済案、古代ギリシアでは自然や人間のうちに働く神々しい力の顕現を指す。 キリスト教ではキリストの十字架における死と復活が両者を統合する啓示とされる。その神学の教義においても、啓示を自然的・世界内在的な現れとするか、超自然的・超越的なそれとするか、異なった見解がある。特に啓蒙主義以降の世俗化は前者を継ぐものであり、人間の理性に創造的な力を認め、歴史の進行を救済史的な啓示の展開過程と見る。 これに対し啓示の超越性・超自然性を強調する神学においては、堕罪に由来する神と人との無限の質的差異ゆえに、啓示は理性に反するもの、他者としてのみ認められる。ゆえに啓示は哲学的概念で捉えることは出来ず、むしろ神学的象徴が手がかりとなる。 啓示と歴史の関係については、その現れには歴史が要されるが、その進行そのものにおいてではなく、それを根拠づけると同時に無化する深淵として啓示はなされる。 |
|
形式 けいしき 独 die Form 希 eidosより 哲学の伝統では、質料(Materie)、内容(Inhalt)、素材(Stoff)に対置され、プラトン以来、それらの個別性・偶然性に対しその普遍性・必然性が強調される。 聖書では、創世記において神が混沌より世界を形作り、土の塵から最初の人間アダムを形作ったことが、形式の神秘性を保障することになる。 世俗化された文化・社会では、それが表面上自律的であれ、宗教から引き継いだ形式が司法、経済、倫理、芸術、教育制度などを支え、権威づける。文化とは宗教の表現形式である、とティリッヒは言う。しかし人間の形式化する能力は神のそれに比し、不完全で歪曲を帯びたものに留まる。ちょうど人間の言語がそうであるように。ベンヤミンは形式化を可能にする人間の言語の抽象能力が、堕罪の産物であると指摘している。純粋な形式は神の下でしか存在しない。ゆえに文化の神学的批判とは、形式の限界を突破する内実の顕現に向かうものとなる。 |
|
形而上学 けいじじょうがく 独 die Metaphysik 希 meta ta physika(自然学の後の)より 元々アリストテレスの著作集のうち、自然学(Physik)に続くものの意。彼によれば「第一の原理および原因についての学」であり、特に「第一哲学」とも呼んでいる。 その後新プラトン主義者たちにより、「自然(physis)を超える(meta-)学」として、知覚世界の背後にある、超越的な原因を対象とする学と見なされた。 形而上学が探求の対象とするものは、存在者としての存在者の、本質および存在、その最終根拠である。それはすなわち他の諸科学のように存在者の特定の制約された側面(例えば医学における身体)をのみ扱うのではなく、存在者そのもの、その全体にして統一体なるものを対象とする。ゆえに形而上学自身、いわば他の諸科学の暗黙の基底となる学である。 後に18世紀ドイツの哲学者ヴォルフは、一般形而上学(mataphysica generalis)としての存在論を、特殊形而上学(metaphysica specialis)としての神学、心理学、宇宙論から区別した。特殊形而上学の対象はそれぞれ、神、魂、世界である。 その対象の次元ゆえ、形而上学の方法には、いわゆる経験科学の記述的・分析的言語使用とは異なったあり方が要求される。伝統的な方法としては類比や弁証法があり、その際言語の象徴的側面が肝要となる。形而上学者により第一の原理は様々な象徴的言語をもって表現される。善のイデア(プラトン)、理性(アリストテレス)、一者(プロティノス)、実体(スピノザ)、モナド(ライプニッツ)、超越論的自我(フィヒテ)、絶対的なるもの(ヘーゲル)、無制約なるもの(ティリッヒ)等である。 他方、こうした超越的原理を否定ないし認識不可能とする立場があり、特に懐疑主義や経験主義、唯物論と呼ばれる思潮がそれにあたる。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 第5号:Metaphysik als erste Philosophie |
|
系譜学 けいふがく 独 Genealogie 希 genea(誕生)のlogia(知) 原義では始祖の探求。特にニーチェ『道徳の系譜学』以降は、理念や思考の思想的・社会的・自然的起源を文献学的に辿る学、価値や規範の歴史的成り立ちを探求によって導き出す学を言う。 参照: 「ありのままの今」を生きる!「超人」ニーチェの言葉 , All About 「ドイツ語」 |
|
啓蒙主義 けいもうしゅぎ 独 die Aufklärung 英 the Enlightenment 元来の意味は、従来暗く不明瞭だった物事を照らし出すこと。思想史においては権威や伝統に思慮なく従うのではなく、理性的批判能力を展開させることによってより高次の知に至ろうとする試みおよびその時代を指す。 ヨーロッパでのいわゆる啓蒙時代は17世紀イギリスで始まり(自由思想家)、フランス(百科全書派)、ドイツへと波及した。術語としての確立は18世紀後期、カント『啓蒙とは何か』(1784年)からである。神学的には理神論の進展による理性的宗教としてのキリスト教のありかたが模索された。伝承された権威より、理性、個人、自由が称揚され、古代ギリシアの啓蒙的学問では主張されるに留まった世界の脱魔術化を現実に推し進めることになった。ただしキリスト教の伝統に対し批判的である一方、それを破棄しようとはしない保守性も併せ持った。 政治的にはフランス革命をはじめとする市民革命に結実し、哲学的には言語、歴史、文化をとりこむことで普遍的理性の絶対性にも疑問を付した。また進歩思想、権力分立、言論の自由、法における生まれついての平等、寛容などが促進された。英仏の啓蒙主義が経験主義的・唯物論的・自然主義的傾向を示したのに対し、ドイツのそれは理性主義的であった。理性偏重は感情や想像力の抑圧を生み、反動としてロマン主義の登場を招くことになる。 参照: 『カントに学ぶ、真の「オレ流」を生きる思考法』、All About ドイツ語 |
|
悟性 ごせい → 知性 |
|
自然 しぜん 独 die Natur 希 phýsis 羅 natura 人工物のように人間の手によるものではなく、自ずから発生・成長するもの。欧語では自然物をそのものとなすもの、つまり「本性」の意も持つ。前者を質量的自然概念、後者を形式的自然概念と分類することも出来る。 自然の事物それぞれに生得の本性を特に認めたのがアリストテレスである。それは各自然物がそれぞれの成長・運動の源を己が内にもつという自発性の現れであり、そうした成長や運動は目的論的にそれぞれ生得に目標を定められているとされる。 しかし神のような高次の存在者を前提とする目的論的自然概念は近代に入り科学の発展と共に廃れて行き、自然法則がそれに取って代わることになる。デカルトによる外延としての自然理解、フランシス・ベーコンによる支配されるべきものとしての自然理解はその思潮に伴うものである。 |
|
実体 じったい 独 die Substanz 希 hypokeimenon(土台), ousia(所有物) 羅 substantia(下に(sub-)あるもの(stanz)) 「本質」と同じく、ギリシア語のousiaからの訳語。 まずはアリストテレスにより、存在者を構成する原理として形成された概念である。 アリストテレスによる定義としては、それは第一に「何か(別)の主体について言われることもなく、何らかの主体の内にもない」もの。換言すれば、それはイデアのような一般的な概念、種や類ではなく、具体的個物としての「このもの」であるということである。 例えば「アリストテレス」という個体で考えてみれば、 「何かの主体について言われることがない」というのは、「プラトンはアリストテレスである」という文が意味を成さないように、何か他の個物の述語になりえないことをいう。 「何らかの主体の内にない」というのは、複数の個体に妥当するような抽象的概念、本質ではないということである。 例えば「アリストテレス的であること、アリストテレス性」はアリストテレスという主体の内にあるもの、その本質であり、「人間はアリストテレス的なるものである」というふうに、複数の主体についての述語ともなりうる。 これに対し「アリストテレス」の実体は何か主体の内にある本質的なものではなく、「人間はアリストテレスである」という文が意味を成さないように当人以外の述語とはなりえない。 アリストテレスはこのような実体を特に「第一実体」と呼び、抽象的概念・本質を指す「第二実体」と区別している。両者の関係はまた、質料と形相、可能態と現実態の区別にも反映している。 さらに個物としてのこのものとは、つきつめれば自立したもの、様々な付帯的な規定(偶有性)の担い手でもある。語源にも示されているように、偶然的なものや変転するものに対し、それらを根底から担いつつも自身は不変のまま持続するものを指すのである。 哲学者による代表的な規定としては、 「自身が存在するために他の事物を要さないもの」(デカルト) 「それ自身の内に在り、それ自身によって把握されるもの、つまり自身の概念形成のために他の事物の概念を要さないもの」(スピノザ) 「現象のあらゆる変転の中で不変であり、その量は自然の内で増えも減りもせぬもの」(カント) などが挙げられる。 実体とは観察や知覚によって認められるものではなく、思弁によって把握されるものである。故にその定義は哲学史でも多様なものとなる。 「イデア」(プラトン)、「個物・形相」(アリストテレス)、「延長実体と思惟実体」(デカルト)、「神ないし自然」(スピノザ)、「モナド」(ライプニッツ)、「心理学的虚像」(ヒューム等経験主義者)等。 世俗化論では一般に、宗教から世俗への移行に実体的連続性を見る。宗教は、(世俗化されたそれであれ)文化の実体である、とティリッヒはいう。レーヴィットも近代の進歩思想を終末論の世俗化と捉えるが、ここには中世から近代へ、同一の実体の連続性が前提されている、として批判を加えたのがブルーメンベルクである。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 第3号:"Philosophen sind diejenigen, ..." |
|
自由主義神学 じゆうしゅぎしんがく 独 Liberale Theologie 19世紀より、特にプロテスタントで盛んになった神学的立場。科学的進歩・実証的研究の成果と信仰を調和させようとする傾向を持ち、ゆえに聖書に記述された出来事も必ずしも歴史的事実とはしない。啓蒙主義や観念論に理論的基盤を持ち、世俗化を肯定的に評価する。現在、西方教会の大半がこの立場を公式にとる。 |
|
象徴 しょうちょう 独 das Symbol 希 symbolon(一緒くたにされたもの)より 古来より様々な定義が為されてきたが、一般には普遍的、抽象的、理念的なものを個別的、具体的、現象的に知覚・直観可能にするものとされる。鳩は平和の、梟は賢さの、百合は純潔の象徴、といった具合に。 ティリッヒは象徴の特性として、1.非本来性(それによって象徴されたものを指し示すこと)、2.可視性(具体的・抽象的であるを問わず、表象可能であること)、3.自力性(記号と異なり代替不可能であること)、4.被承認性(社会的にそれと認知されてあること)を挙げている。 美学用語と見なされがちだが、把握しがたいものとの結びつきと隔たりというその二義性は、神の似姿と堕罪という人間の二義性を自身象徴している。ゆえにその権限を神学の領域におくものであり(ベンヤミン)、宗教の直接的表現を可能にする唯一の言語である(ティリッヒ)。 |
|
自律 じりつ 独 die Autonomie 希 autos(自己の) ∔ nomos(法)より 国家、個人、文化現象などについて、それを構成する法が外的な権威によってではなく、それ自身によって与えられてあること。 哲学では特にカントの実践哲学において、理性的存在である人間が実践的理性によって自分自身に、自らそれに従って行動すべき普遍的法則を与える自己規定を指す。これはあらゆる被造物のなかで人間のみに可能とされる。 世俗領化や世俗化の基本的な図式においては、教会という権威による宗教・政治上の他律から、国家や個人の自律への移行が推し進められる。 自律的文化において目指されるのは、その形式の成就である。芸術作品では、形式の調和と完成が重視される。 |
|
神学 しんがく 独 Theologie 希 theos(神)+logos(教説)より その語がギリシア語に由来するように、神学の起源は哲学と同じく、古代ギリシアに遡る。クセノファネス、プラトン、アリストテレスは、ホメロスやヘシオドスらによって伝承された神話の神々の姿に不当な人間化を見て取り、そのあるべき神性を取り戻すべく批判を加えた。そもそも神なるものとは「第一にして最高の原理」である、とアリストテレスは言う。この神の教説における詩的・伝承的要素と理性的要素の対立は、以後も神学の発展において基調をなすものである。 このギリシアの神が、自身は自然の根底にある静的な不動者とされるのに対し、聖書の神は歴史に内在的かつ超越的に働きかける動的な神である。アレクサンドリアのクレメンス、オリゲネス、そしてアウグスティヌスといった初期教会の教父たちは、特に異教徒に対する弁神論としてキリスト教神学を礎を築いていった。12世紀よりのアリストテレス哲学受容がさらに神学の体系化を推し進め、中世最大の神学者トマス・アクィナスが、至高の学としての神学を「神学の婢女」としての哲学との関係付けによって確立することになる。 宗教改革以降の近代神学は、信仰と知を、綜合・二者択一・並置といった様々な関係のなかで問い直してゆく。特に神学の座を揺るがせることになったのは啓蒙主義、それもカントによる理性批判であり、ここで神の存在証明を代表とする学としての神学は疑わしきものとなり、信仰と知は分離されることになる。その一方、あくまで両者の綜合を目指したのがドイツ観念論、特にヘーゲルとシェリングの哲学的神学である。 さらに19世紀後半より、フォイアーバッハやマルクス、ニーチェやフロイトといった、宗教そのものの仮借ない批判者が登場する。また進化論を始め自然科学の発展が宗教的世界観を揺るがせることになる。これに対し可能な限り協調し発展してゆこうとする立場がいわゆる自由主義神学、あくまで啓示の源泉として聖書に顕れた神の言葉に基づこうとするのがバルトらの弁証法神学である。 啓示の源泉を自然に見るか聖典にのみ認めるか、信仰と理性をいかに関係付けるか。こうした問いかけにより神学の構成もその歴史を通じて多様なものとなる。 世俗化論においては、「現代国家理論のあらゆる重要概念は、世俗化された神学概念である」(カール・シュミット)、「あらゆる歴史の哲学は、神学に余りなく依存している」(レーヴィット)といった言明にみられるように、特に諸学の神学への隠れた関係が問われることになる。 |
|
神律 しんりつ 独 die Theonomie 希 theos(神) ∔ nomos(法)より 自己自身の法に基づく自律に対し、神の法に基づくあり方をいう。しかし他律のように外的な(特に宗教的)権威によるのではなく、自律がその極限にまで深められることによって顕現に至る。それゆえ他律から自律への移行を図式とする世俗化は、制度的宗教の解消という形をとりつつも、実際には真の宗教性である神律への不可欠の過程であるといえる。 神律的文化においては宗教と文化が本質的合一にいたる。そこで目指されるのは内実の表れであり、芸術作品では形式の強度と破壊という形をとる。 |
|
神話 しんわ 独 der Mythos 希 mythos(言葉)より 神々や精霊、世界の始まりや終わりといった物事に関する伝承。ギリシア神話、北欧神話など個別のものを指す他、現代の神話などと比喩的に用いられもする。聖書の物語りも様々なオリエントの神話が元になっているとされる。 古代ギリシアにおける哲学の成立を「神話からロゴスへ」の移行と称するように、迷信・迷妄と見なされがちである。しかし実際にはあらゆる宗教・文化の実質をなすものであり、その根源的な意味においては真理を直観化するものとして、少なからぬ神学者や哲学者の関心を得ている。一方では神話の批判者であるプラトンも、万物への「驚き」を共有するという点で神話を哲学の友と見なしている。 キリスト教にとって神話は、神というロゴスのために克服すべき異教的要素でもあれば、生きた信仰を可能にするために不可欠の媒介でもあった。中世に盛んであった寓意的解釈は神話活用のための方法の一つである。 啓蒙主義は神話を迷妄と見なしたが、ロマン派や観念論者は神話に新たな評価をもたらすことになった。 |
|
枢軸時代 すうじくじだい 独 die Achsenzeit ヤスパースが『歴史の起源と目標(Vom Ursprung und Ziel der Geschichte)』で提唱した歴史哲学的概念。具体的には紀元前800~200年ごろ。 この時代、中国、インド、ギリシア、中東等で、相互の交流を持たないにも関わらず、数多の思想家の登場により、史上初の哲学の萌芽が見られた。孔子、老子といった中国の思想家、仏陀やゾロアスターといった教祖、パルメニデスやプラトンらの哲学者、イザヤやエレミヤ等の預言者のことである。 彼らによって初めて、存在そのもの、自己、そしてその限界が意識に上り、自明なものとしての世界が疑問視された。その疑問は神話にもおよび、神性の純粋さも問われることになった。それは同時に人間が己の理性、人格を意識するのに欠かせぬ過程でもあった。 ヤスパースの著名に明らかなように、枢軸時代という概念は歴史の「起源」を知り、同時に歴史そのものの「意味」を問うがために提起されたものであり、超宗教的視野を持つにもかかわらず、聖書的救済史観に基づくものである。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 第2号:Die Achsenzeit |
|
世界の脱聖化 せかいのだつせいか 独 die Weltentheiligung 宗教改革によって信仰が個人化、内面化され、それに伴いカトリック教会が保持してきた自然界や諸権威の聖別化が解消されること。カムラーは特にルターのそれを指している。俗化と異なり、学問や技術の促進に(少なくとも直接には)組せず、あくまで信仰が重視される。ルターは教会権力から自由な世俗の権威をキリスト教の立場から正当化したが、俗的制度、つまり神の創造への畏敬に基づかないような制度や運動は求めていなかった。 |
|
世俗化 せぞくか 独 die Säkularisierung 英 the secularization 羅 saeculum(世代、100年)に由来。 世俗領化が転用された概念。リュッベやカムラーによる世俗領化と世俗化の区別は、世俗領化は法的・政治的概念だが、世俗化は文化史的・歴史哲学的概念であるという点にある。より簡単に言えば、世俗領化が物質的財産の移し変えであるのに対し、世俗化は精神的道徳的財産の移し変えである。ゆえに修道院が引き渡されプロテスタントの聖書学校に転用されるのは世俗領化であると同時に世俗化でもあるが、カトリック教会から収奪されるものが例えば領有していた森林であった場合は、それ自体がキリスト教的な財産でないゆえに、それは世俗領化されたのであっても世俗化されたのだとはいえない。 世俗化の具体的な例は次の通りである。西洋の病院では、女性看護師は(たとえ彼女が修道女でなくても)<シスター(Schwester)>と伝統的に呼ばれる。また<兄弟(Bruder)>という言葉も、キリスト教ではその最初期より信徒相互の呼び合いに用いられ、そのまま<友愛(brüderliche Liebe)>や、自由・平等と並ぶフランス革命の理念である<博愛(Brüderlichkeit)>という言葉に世俗化されることになった。すべての人間が兄弟になるという『第九』の理想は、キリスト教終末論の遺産を言葉として引き継いでいる。 その一方で、離婚や姦淫、自殺を道徳的に許容しない風潮は、少なくとも西洋では聖書ないし教会の伝統に由来するものである。聖書に由来する肯定的な規範としては、神の前での万民の平等という理念がある。これは民主主義はもちろん、共産主義にまで引き継がれている理念である。 つまり、世俗化によって引き継がれ、残り続けてゆく要素の代表格は、語彙や言い回しといった言語的要素(例えば<兄弟>)並びに道徳的規範(例えば自殺の禁止)である。ただしそうした中でどの要素が保持され、どの要素が失われるかは予測されえない。それは後述するように、世俗化の遂行者、その主体が匿名であり、その進行が盲目的であることに関わっている。 その世俗化という術語が西洋社会で広範に認知されるのは19世紀以降のことである。イギリスやドイツで特に学校教育での教会からの解放に用いられ、文化闘争や自由思想を表す言葉ともなったのだ。それから認識に関する用語として学術語の一つに認められた。学問の世界ではまず哲学の分野でこの概念は脚光を浴びることになる。ディルタイやレーヴィットは啓蒙主義の歴史哲学は、アウグスティヌスに始まる歴史神学を世俗化したものに他ならないと述べる。同様にして、実存主義哲学は世俗化された神学であり、カント倫理学は世俗化された福音派の倫理、解釈学は世俗化された聖書釈義だといった言い回しが用いられるようになる。 世俗化に対する保守的神学者の見解は否定的なものになるか、あるいはせいぜい妥協しつつ受け入れるといった姿勢とならざるをえない。そうしたなかで神学者ゴーガルテンは、世俗化はキリスト教の必然的継続を意味すると主張し、むしろそれを神学的観点から肯定的に評価する。曰く、そもそも聖書の超越神がそれ以前の神話的世界から人間を解放し人間に世界を明け渡したのであり、それは世俗化の発端なのだ。例えば創世記の記述からすれば、太陽も星々も、海や山も、神が世界の一機能として作ったものであり、神話のようにそれ自体が神であったり神格化されたりするものではない。聖書の中にそもそも世俗化の、世界の脱神話化の契機が含まれているがゆえに、キリスト教の信仰そのものが世俗化を促進し正当化することになる。近代誕生の契機はキリスト教を世俗化したことではなく、むしろキリスト教によって世俗化されたことにある、というわけだ(ただし彼の用いる世俗化概念は、別項の俗化にも相当する)。 さらにカムラーが挙げる世俗化概念の要素として、その匿名性が挙げられる。我々は例えば世界の脱聖化 はルターによって、啓蒙化 はヴォルテールやデカルトの思想や言述によってもたらされたということができる。だが、世俗化が何をもたらしたかについては上述のように個別例によって確認しうるものの、誰がそれをもたらしたのかその主体は明らかではない。とはいえ世俗化は自然の進行のように自ずから生ずる過程ではなく、あくまで人間の行為によって初めて生み出される。それは匿名の主体による歴史的変容なのだ。 |
|
世俗領化 せぞくりょうか 独 die Säkularisation 一般に言う世俗化の本来形。宗教的財産および支配権を、世俗の権力に委ねること。具体的には宗教改革期における、教会財産の没収が始まり。世俗化に対し、歴史学・政治学的言述のものとして制限される。 |
|
俗化 ぞくか 独 die Profanisierung 俗化とはかつて神聖であったものがその威光を失い、後の時代には俗なもの、人間に支配されうるものとみなされるという歴史的変容を表す。例えば聖書を初めとする諸宗教の聖典は、現在ではもっぱら歴史学的文献学的研究の対象とみなされる。同様に聖画や聖像、祭壇も美術史学的興味によって鑑賞される。かつて神々しいものであった星空を、今日我々は天文学的法則の下にあるものとして理解する。このような点で俗化は、ウェーバーのいう世界の脱魔術化とほぼ同義である。俗化された世界とは、神々と宗教が失われ、もはや恐れを知らぬ人間によって意のままになるような世界を言う。 カムラーが強調するのは、俗化という概念の包括性である。それは厳密に言えば聖対俗という対立も超えている。というのも、俗化が対象とするのは儀式、神話、宗教的行為、振る舞い、話法、習慣といった聖なるものを取り巻くあらゆるものの解消であるから。これらの対象は、それ自体が聖なるものであるとは限らないのだ。 俗化は一般的には世俗化をも包括する概念である。いわゆるキリスト教の世俗化は、俗化の西洋における最も重要な一形態だと考えられる。世俗化は専ら個別の事象を指し、俗化は包括的全体の傾向を示すものとカムラーは解している。その進行が匿名の主体によって成されるという点では両者は同じだ。ただし近代の誕生をキリスト教の世俗化として解する観点は、例えば西洋の学問が古代ギリシアに由来するという一面を覆い隠すことになってしまう。西洋近代文明の成り立ち全てを世俗化に帰するゴーガルテンのような見解は、彼に言わせればキリスト教のための最後の護教論にすぎない。さらに言えば、俗性というものが宗教を失くした状態であり、俗化がそこへ至る過程だとすれば、その過激な形態は世俗化と明瞭に袂を分かつものとなる。つまり世俗化においては言い回しやモラルなど、何らかの要素が変形されつつも保持されてきた。過激な俗化ではそうした宗教的残滓は破壊され、抹消させられることになる。 還元すれば両者の違いは、宗教的実体が何らかの形で保持しようとされるか否かにある。 世俗化が徹底化して俗化となるような場合もある。例えば近代の自然科学は古代ギリシアの学問と結びつくのみならず、キリスト教の創造神信仰によって促進されても来た。つまり、世界が神による創造物であるゆえに、その探求は信仰に基づく仕事となる。そしてあらゆる被造物が等しく卑しく等しく崇高であるゆえに、探求の対象も偏向なく広がることになる。だがこのような自然探究の動因としての信仰は次第に忘れ去られてゆく。そしてもともと創造神信仰の世俗化であった探究欲が、ついにはキリスト教の遺産の抹消することになる、つまり過激な俗化に行き着くのだ。 |
|
存在 そんざい 独 Sein 英 being 仏 l'être 希 on 羅 esse 印欧語においてはその術語が「~が在る」と共に(繋辞として)「~である」を意味するため、西洋哲学の伝統では在ることのみならずそれに伴う諸属性(特性、関係、価値等)の源という意も含むことになる。すなわちこの言語上の観点からすれば、存在は本質と分かちえないということになる。 これに対し、両者を峻別する、つまり存在を在ること(existieren)に限定しようとする把握を、カントやキルケゴール、さらにはトマス・アキナスによるextenitaとessentia、ハイデッガーによるSein(存在)とSeiendes(存在者)の区別に見ることができる。 逆にプラトンやヘーゲルらは、存在と本質に連続性を見る。あらゆる現象は存在の弱度の表れと見なされ、その彼方には存在の充溢、すなわち絶対者や神と呼ばれる存在がある。両者の間には存在の度合いに応じて様々な段階がある。 前者を実存主義的、後者を本質主義的な存在把握と呼ぶことが出来よう。これはいわば、神による世界創造における「無からの創造」と「流出」の両説の対立が世俗化されたものである。 実存主義的把握からすれば、存在は世俗化の限界を意味する。つまり神的な本質とみなされる諸属性が世俗化されてゆく一方、存在そのものをもたらす力は世俗化されえない。 |
|
存在論 そんざいろん 独 Ontologie 希 on(存在) + logos(教説)より 在ることとは何かを問う学であり、存在者がそれなしに存在しえぬような原理についての教説。 「存在論」という哲学の術語は17世紀に作られたものであるが、「在る限りにおいて在るもの、およびその在ること自体に付随するのは何かを考察する学」は既にアリストテレスが「第一哲学」として提唱し、「形而上学」として引き継がれたものである。しかしアリストテレスはこの学を「在るものとしての在るものの第一根拠」、すなわち神についての学と同一視した。以後存在の学は特に神学との関係をめぐって展開することとなる。 18世紀ドイツの哲学者ヴォルフは存在論と神学を理論上はっきりと区別し、存在論を一般形而上学(mataphysica generalis)に、神、魂、世界に関する学としての神学、心理学、宇宙論を特殊形而上学(metaphysica specialis)に分類した。 存在論はしかし神学と共に、カントにおいて思弁的哲学の領域からは追放されることになる。つまり彼の超越論的哲学は両者の扱う対象を、人間の経験上可能な認識能力を超えたものとして、認識論的に不当なものと見なす。これに対しフィヒテ、シェリング、ヘーゲルらによるドイツ観念論は、いわば認識に存在論的次元を回復しようとする試みである。とりわけヘーゲルはその論理学において、認識の原理と在るもの自体の原理を結びつけることによって認識論と存在論の分裂を止揚し、さらにその原理を神ないし絶対者によって根拠付けることで、存在論と神学を再度統合することになる。 20世紀になって存在論はハイデッガーにより新たな評価を得る。彼は存在(das Sein)は存在者(das Seiende)とは全く別の在りかたで在るとし、プラトン以来の西洋哲学史に両者の混同という視点から批判を加えた。 |
|
堕罪 だざい 独 der Sündenfall
創世記では、最初の人間アダムとその妻エバが神の命に背き善悪の知識の木の実を口にし、そのために楽園を追放されたとされる。これが人間の最初の堕罪であり、哲学的には本質から実存への転落とされる。神の似姿性と共に、ユダヤ・キリスト教の人間像を他の被造物から分かつ根拠となる。 ベンヤミンはこの堕罪の出来事に、特に言語精神のそれを見て取っている。命名が創造であった名の言語が、間接的伝達の道具や記号のようなものとなったこと。善悪の認識と共に生じた、裁く言葉、判決の能力。具体的な名を持たぬ、抽象化の能力。この三つが言語精神の堕罪とされる。 |
|
他律 たりつ 独 die Heteronomie 希 heteros(他の) ∔ nomos(法)より 国家、個人、文化現象などについて、それを構成する法が外的な権威によって与えられてあること。 哲学では特にカントの実践哲学において、自己自身の理性に基づく道徳法によらぬような意志は、他律的とみなされる。 世俗領化や世俗化の基本的な図式においては、教会という権威による宗教・政治上の他律から、国家や個人の自律への移行が推し進められる。 他律的文化で目指されるのは、その内容の成就である。芸術作品では、宗教・政治的モチーフやイデオロギーが重視される。 |
|
知性 ちせい 独 der Verstand 英 understanding 仏 entendement 人間を他の動物から区別する、専ら能動的な認識能力の一つ。悟性とも称される。類した能力に「理性」があるが、カント以降両者の術語としての関係は逆転した(→理性)。 理性が全体性や経験を超えた認識、直観に関するのに対し、知性は経験しうるものの論述的・分析的・内省的・批判的・段階的認識、概念形成や判断に関わる。特に概念形成のため、知性は感性によって受動的に知覚された像を必要とする。 |
|
定言名法 ていげんめいほう 独 kategorischer Imeprativ カントによる倫理学の術語。客観的原理として意志が従うべき理性法則。仮言的命令が「裕福になりたければ、労働せよ」のような条件付の命令、何か別の目的のための手段としての行為を促す命令であるのに対し、定言的命令は無条件かつ普遍的になされる命令、行為それ自身のための行為を促す命令。従ってその際、意志は対象には依存しない。 『人倫の形而上学の基礎付け』での表現はまず、「ただその格率が普遍的法則となるよう、君がその格率によって同時に欲しうるような、そんな格率にのみ従って行為せよ(handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde)」。「格率」とは行動の主観的原理、法則とはそれに従って行動すべき客観的原則をいう。人間の本質の全体性において、具体的状況で、為になる行為は良いものであり、普遍化しうる。 その他、以下のように表される。 「君自身の人格にも他の皆の人格にも例外なく存するところの人間性を、常に同時に目的として用い、決して単に手段としてのみ使用しないように行為せよ」(Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.)(『人倫の形而上学の基礎付け』) 「君の行為の格率が、君の意志によってあたかも普遍的自然法則となるかのように行為せよ」(handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.)『人倫の形而上学の基礎付け』) 「君の意志の格率がいかなる時も同時に普遍的立法の原理として妥当しうるよう行動せよ」(„Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“)(『実践理性批判』) 参照: 『カントに学ぶ、真の「オレ流」を生きる思考法』、All About ドイツ語 |
|
哲学 てつがく 独 Philosophie 希 philosophia(知への愛)より 哲学、特に西洋哲学の源は古代ギリシアにある。自然を統べる根源的原理(アルケー)の探求から始まった哲学は一時徳を含む理論的な生活知へと陥ったが、ソクラテス・プラトンにおいて、哲学者とは己の限定された知を知り、なおかつ人知を超えた知への愛に駆り立てられたものである、と、その普遍的理念が取り戻された。さらにアリストテレスは本来の哲学を特に<第一哲学>(形而上学)と呼び、その課題を存在の第一根拠・原理を探ることにあるとした。スコラ学派になって哲学は、形而上学・自然学・倫理学に大分される。さらに近代になると、デカルトやカントにより認識論、バウムガルテンにより美学といった新たな分類がこれに加えられる。 哲学は真理の探究という点で、神学と一致を見る。アレクサンドリア学派、アウグスティヌス、トマス・アクィナスからデカルトやヘーゲルといった近代の哲学者まで、哲学は絶対者としての神の理念に基づくものとして、神学の発展と分かちえぬ関係にある。 その一方、「アテネがイェルサレムに何の関わりを持つというのか?」(テルトゥリアヌス)や「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であり、哲学者や知識人の神ではない」(パスカル)といった、純粋な信仰という立場から福音の哲学的解釈を批判する声もあがることになる。 近代において哲学が神学に最も接近しているのが、いわゆる実存主義哲学であろう。これによれば、認識論をはじめあらゆる哲学的問いは存在という前提において初めて可能となるゆえ、哲学の根本問題は存在論ということになる。ティリッヒは、存在の構造と、その記述のためのカテゴリーや概念に関わるのが哲学、その存在の意味に関わるのが神学であるとして両者を区別している。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 サンプル号:Staunen als Anfang der Philosophie |
|
名 な 独 der Name 創世記第2章19節によれば、神の世界創造は最初の人間アダムがあらゆる生き物を名づけることによって一つの成就を見る。ここでは名において創造と認識が一つであり、神と人間、人間と自然の罪なき宥和状態が保障されている。 言語精神の堕罪とはこの名の神秘的力の喪失であり、言語の救済とはそれを取り戻さんとする試みである、ととりわけショーレムやベンヤミンといったユダヤ系思想家は強調する。このユダヤ的言語思想は、ヘブライ語で<言葉>を意味するdavarは同時に<物>をも意味するという事実にも表れている。 |
|
内実 ないじつ 独 der Gehalt かつては内容(Inhalt)と同義で用いられていたが、近代以降の美学では特に芸術作品の内的価値、本質などを指す。ヘーゲル美学では作品の個別形式において現れる一般的なるもの、知覚化された理念であり、ゲーテにおいては<内的形式>とみなされる。 ティリッヒの文化神学では、それは形式に初めて意味をもたらす精神的実質性であり、作品の内容において(an einem Inhalt)、形式を媒介として(mittels der Form)、表現へともたらされる。ある作品において形式による自律が内実の過剰に耐えられなくなった時、内実は形式を突破して自身を啓示する。表現主義芸術に代表されるそのような作品のありかたは神律的と称される。 ベンヤミンにおいては形式化する原理がギリシア的ないし神話的原理と称される一方、形式を克服する原理はオリエント的ないし神的原理と呼ばれる。後者の顕現のために前者の媒介が要されるのは、ティリッヒの場合と同様である。 |
|
バベル Babel ヘブライ語の都市名Bavel(神々の門)より。聖書によれば似た響きの「混乱」を意味する語とも関係する。
創世記11章にあるバベルの塔の逸話による。つまりかつて世界中の民が同一の言葉を話していたが、彼らが天に達する塔を持つ町を作り名を成そうとしたことに対し、神は彼らの言葉を混乱させ全地に散らしたことでこれを妨げた。ユダヤ・キリスト教の伝統では諸言語の差異の起源であり、人間の堕罪の一つである。 ベンヤミンは自身のボードレール訳への序文で、翻訳者の使命は異なる言語をそれぞれ伝達の道具という意味連関から切り離し、そこから一つの真なる言語(純粋言語)への憧れを呼び起こすメシア的行為にあるとしている。バベル的多言語状況は神学的には罪の現れであるが、その罪を罪と知らず一つの言語の制約に自足することがむしろ救済への道を閉ざすことになる。 |
|
卑俗化 ひぞくか 独 die Profanierung 英 the profanation 羅 profanatio 俗化の原義というべき語。 聖なるものを個人的に冒涜する行為を指す。例えば兵士が教会を馬小屋として用いたり、ごろつきが聖杯を酒盛りに用いたりするような涜神的行為(日本で言えば、仏像を砕いて薪にするようなものか)。ただしカムラーの分類では転用された概念である俗化と異なり個人的な行為に留まるもので、歴史的変容を意味しない。そして聖と俗との境界を半永続的にゆるがすものではない。 |
|
批判/批評 ひはん/ひひょう 独 Kritik 希 kritikē [téchnē](判断術)に由来 哲学の術語としては、カントの『純粋理性批判』以降、認識能力の<限界付け>といった意で用いられる。もちろん<限界>づけることとは後ろ向きな意味のみならず、それが指し示しうる可能性も含意する。その二義性の根底には、神の似姿とそこからの堕罪としての人間像がある。 さらに特にロマン派により芸術作品の<批評>として、作品を限界づける以上にその可能性を展開させる創造的能力として新たな把握が与えられてゆくことになる。 批判が限界付けである以上、その限界を超えるものとの関係は解消できない。限界を超えるものとの関係が穏健であれば批判は形式的なものとなるが、その関係が強くなれば、その形式を突破する内実の表現形式となる。批判が目指すところが形式に留まるか内実に向かうかが、その批判が神学的であるか否かを決定付ける。 |
|
文化の神学 ぶんかのしんがく 独 Theologie der Kultur 英 Theology of Culture 1919年にティリッヒが行った講演『文化の神学の理念について』に由来する、主にプロテスタント神学上の術語。 文化学の一部門をなし、宗教哲学的カテゴリーに基づきつつ、具体的な文化現象(特に芸術)を規範的に叙述しようとする試み。いわゆる世俗の文化を対象とし、文化における宗教と世俗の対立を止揚することが目指される。 |
|
本質 ほんしつ 独 Wesen, Sosein, Washeit 希 ousia, to ti en einai 羅 essentia, natura, quidditas 英 essence 「実体」と同様、ギリシア語のousiaに由来する術語。 第一に、それはある存在者が本来的にそれ自身であるのに不可欠な諸特性、つまりあるものをそれたらしめるものを指す。例えば古典的な定義で言えば、人間の本質とは理性の使用にあり、それを失えばもはや人間ではない。 そしていかなる状況においてもその存在者において変わらざるものという意味で、本質は「実体」と同義と見なされ、「偶有性」や「現象」に対置される。 スコラ学者は本質をさらに、ある対象を定義する概念、そして現象としてのある対象の背後にある不可知の根拠、として二重に規定した。 他方で本質を、ある存在者において「ある」ものではなく、その存在者が「なる」べきものと見なす解釈もある。例えば種子の本質は花を咲かせること(アリストテレス)、歴史の本質は自由な国家を実現すること(ヘーゲル)にある、といったように。種のうちに潜在する目的の実現をその本質とする、目的論的解釈である。 それはまた本質に、「かくあるべき」という規範的属性を認めることでもある。 本質を個物に認めるか、個を超えたもの、あるいは普遍的なものに認めるかは、これも解釈が分かれる問題である。しかし上の、「不変にして持続するもの」という本質の定義からすれば、本質とは例えば「田中一郎」という定命の個人によりも、むしろ「人間」や「生物」といった彼が属する種や類に認められることになる。つまりアリストテレスの言う、第一実体ではなく、第二実体がこれに相当する。もっともこの解釈も、例えば種や類の持続を否定する進化論とは折り合わない。 哲学史において、合理主義の立場からは本質は知覚に依らず、理性の使用によってのみ認められるものとされる。 一方で経験主義の立場からは、知覚に依らぬ認識はありえず、本質は実在するものとは見なされない。特にロックは、スコラ学派の分類を引き継ぎ、本質を実在的本質(real essences)と唯名的本質(nominal essences)に区別し、前者を現象の根底に在るもの、実体としての本質、そして後者を概念の定義のために用いるもの、ものに本質的名称を与えるために要するものとした。経験主義の見地からすれば、両者のうち実在が認められるのは後者、唯名的本質のみである。 参照: 『ドイツ語で哲学を』 第4号:Was heisst das Wesen? |
|
無からの創造 むからのそうぞう 独 die Schöpfung aus dem Nichts 羅 creatio ex nihilo 神による世界創造説の一つ。原初の無から、神の意思により世界が創造されたとする教説。 特に聖書的根拠は持たないが、1215年に第4回ラテラノ公会議において、キリスト教会の教義とされた。 流出説とは逆に、神の超越性が保障されるが、その世界への関わり方、内在性が不明瞭となる。換言すれば、個々の存在者や歴史的・文化的段階に神性の度合いの違いが認め難い。 |
|
ユダヤ教 ゆだやきょう 独 das Judentum 創世記29章35節、ヤコブの四男Judahの名に由来 イスラエルより世界に離散(Diaspora)された民族の宗教で、19世紀よりその民族そのものの呼称ともなった。いわゆる旧約聖書と、タルムードと呼ばれる口伝教説を経典とする。タルムードは律法(Halachah)と教訓的寓話(Agadah)を含む。 ダヴィデの星と呼ばれる六芒星をその中心象徴とする。 特にドイツ語圏を中心とするヨーロッパで、キリスト教側の啓蒙化の影響下、ユダヤ系独自の文化的・学問的伝統が作られてゆくことになる。 その担い手としてマイモニデス、メンデルスゾーン、コーヘン、ローゼンツヴァイク、カフカ、ブーバー、ショーレム、ベンヤミン、レヴィナス、シャガールといった名が挙げられる。 <ユダヤ的>といった場合、伝統を共有するキリスト教とよりも、<ギリシア的>あるいは<神話的>との対比で用いられることが多い。 キリスト教側の世俗化と問題意識を共有しつつも、その同化できぬ差異から批判的に独自の伝統を作り上げていったことが注目に値する。言語および歴史哲学の相違が特に強調される。また離散や流謫(Exil)、虐殺(Pogrom、Holocaust)といった民族体験から生じるニヒリズムが、特に現代神学の神義論・メシアニズムに宗教を超えた問題意識を投げかけている。 ちなみにイエスはユダヤ教徒にとっては、メシアではなくラビの一人に過ぎない。 |
|
理性 りせい 独 die Vernunft 英 reason 希 diánoia/noûs 羅 ratio/intellectus 一般に、人間の精神に備わる普遍的認識能力を指す。この意味で「知性」の類義語だが、カント以降、術語として両者の関係が逆になったことには注意が必要である。つまり古来ドイツ語ではVerstand(知性)が形而上学的認識能力(noûsやintellectus)、Vernunft(理性)が論証的思考能力(diánoiaやratio)を担うものとされていたのが、カントによって両者の関係が逆となったのである。両者を峻別したのもカントが嚆矢であり、理性は経験を超えた理念、物自体、認識の全体性や統一性、魂、神、世界といった領域に関わるものとされる。また、自由や道徳性は現象ではなく物自体に関わるものであるため、実践的理性の問題となる。 ヘーゲルにとっては知性とは概念を固定するものであるのに対し、理性とは概念を様々に対立させ弁証法的止揚へともたらす、運動性の根源である。また個人がそうした客観的・普遍的理性へと導かれる過程が歴史であるとされる。 |
|
流出 りゅうしゅつ 独 die Emanation 羅 emanare(流れ出す)より 神による世界創造説の一つ。原初の一者が、自身の過剰によりあふれ出て世界を創造して行くとする教説。 グノーシス派や新プラトン主義などはこの説による。 無からの創造説とは逆に、神の世界への関わり方、その内在性を説明できる。つまり、個々の存在者や歴史的・文化的段階に異なった神性の度合いを認めることが可能となる。がその一方で、神の超越性は損なわれることになる。 汎神論的傾向を帯びるが、神と世界が同一というわけではない。 |
|
ルサンチマン 独 das Ressentiment 仏 ressentiment 元々は以前の感情、特に傷つけられた自意識や怨恨が消えず心理的に生き残っていくこと。それはまた繰り返しによって復讐の念となりうる。 ニーチェの用語としては、弱者が「高貴な者」や「強き者」にむける無力さからの憎しみであり、特にキリスト教の普及がその感情をもって説明される。 |
|
歴史 れきし 独 die Geschichte 希・羅 [h]istoria 原義では生起したこと、およびその叙述を指す。 西洋での歴史の起源は、まず古代ギリシアの歴史家ヘロドトスやテュキュディデスに遡る。彼らにとって歴史記述とは、出来事を後世に、特に実践的な目的のために、報告することにあった。 これに対しもう一つの起源である聖書の伝統においては、歴史とは約束された未来の救済、神の国の到来への過程として過去を解釈する行為であり、特に神に対する人間の倫理的堕落および発展が焦点となる。 線的に進行する聖書の歴史的時間は、循環するギリシアの神話的時間にしばしば類型的に対置される。 世俗化論では特に西洋の歴史哲学およびそれに発する進歩思想を、ユダヤ・キリスト教の終末論の世俗化された形態と見る。その代表は世俗化された神の国として絶対精神の実現をおくヘーゲル、無階級社会をおくマルクスの歴史哲学である。 |